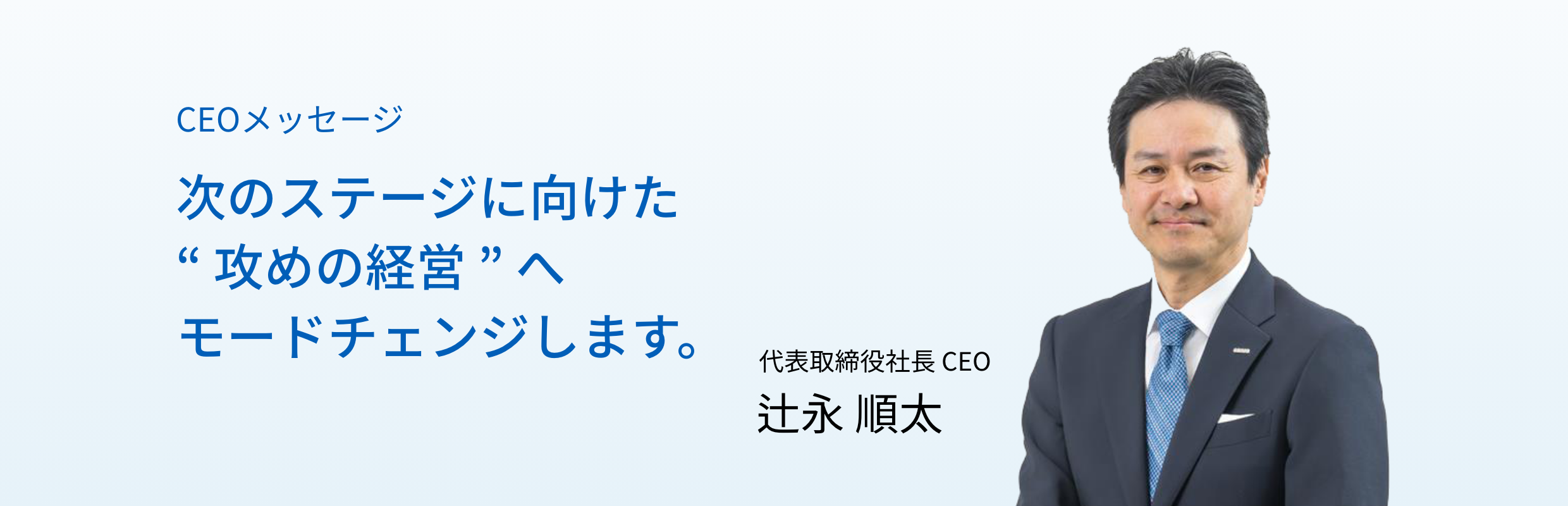
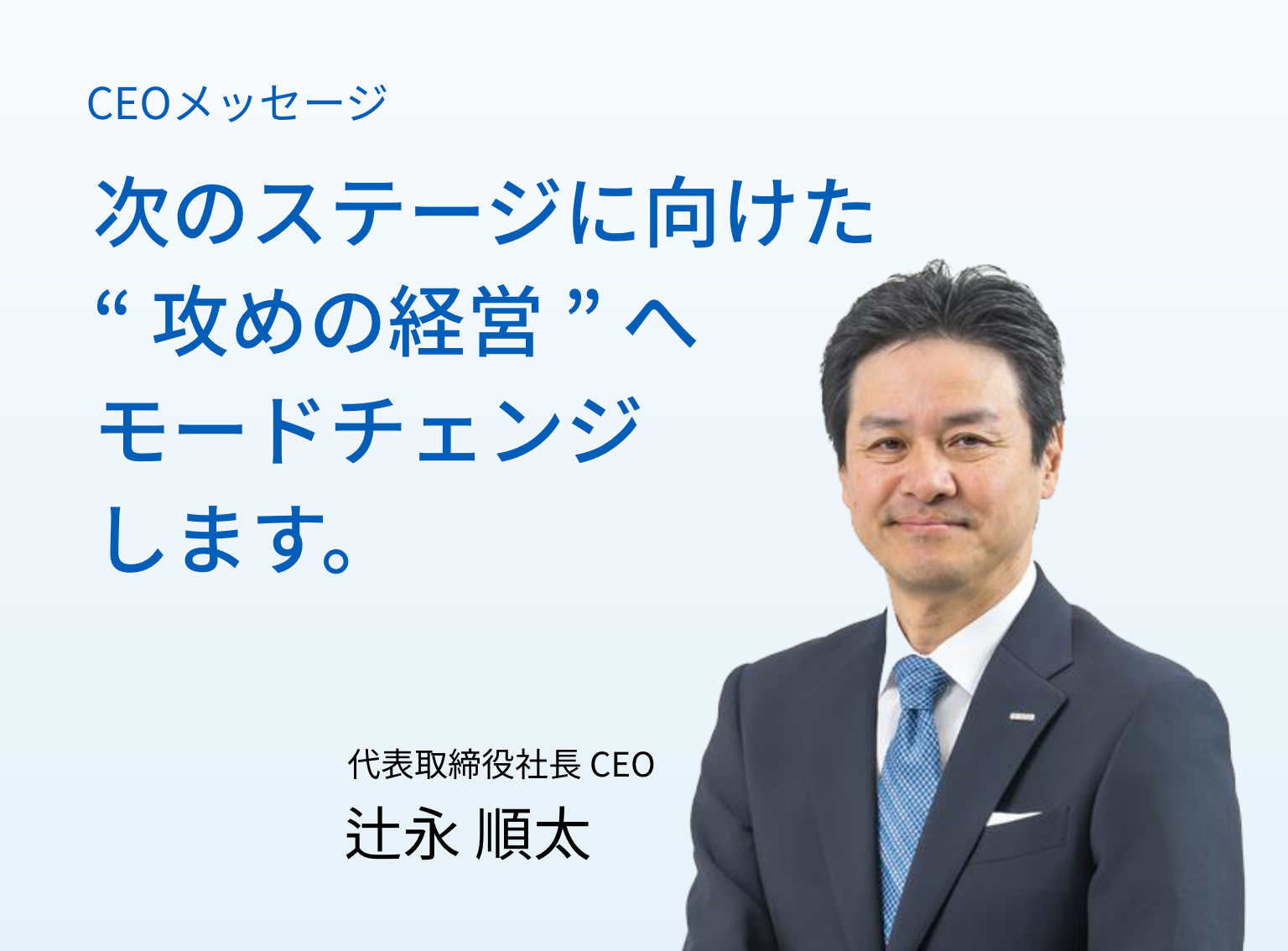
2024年度は、全社方針として「All for creating customer value ~すべてのアクションを顧客にとっての価値の創出に集中させ、収益・成長基盤を再構築する~」を掲げ、顧客にとって価値を生み出すものに集中することで投資効率を高め、「売上にこだわった業績の立て直し」と「収益・成長基盤の再構築」の実現に取り組みました。
「売上にこだわった業績の立て直し」においては、顧客起点で売上を最大化することに全社で注力しました。例えば、制御機器事業(IAB)では、事業基盤の再強化や新商品の開発・上市を着実に進めることで、下期にかけて緩やかに改善した市況を確実に捉えました。その結果、IABは売上の回復と営業利益の大幅な増益を達成し、全社業績を牽引してくれました。この一年でIABを復活させる道筋が整い、全社業績で増益を達成しました。
「収益・成長基盤の再構築」においては、2024年4月にスタートした構造改革プログラム「NEXT2025」で掲げた4つの経営施策を計画通り着実に推進してきました。例えば、「固定費生産性の向上」においては、2024年度だけで約260億円の固定費削減を実現し、2025年度までの削減目標300億円の達成を確かなものにしています。「人員数・能力の最適化」は2024年度中に完遂。「ポートフォリオの最適化」と「顧客起点マネジメントシステムの導入・運用」については、2025年度以降の成果出しに向けた準備が計画通り進捗しました。私はCEOとして、これらの取り組みを通じて全社の稼ぐ力が確実に戻ってきた手応えを掴むとともに、再成長への強い自信を深めています。
※ 詳細は2024年度全社業績(NEXT2025実績含む)をご覧ください
※ 詳細はSTRATEGY & BUSINESSをご覧ください
これらの取り組みを推進するにあたり、私が最も拘ってきたのは「私たちの活動をどれだけ顧客に向いたものに変えられるか、そしてそれをいかに持続できるか」です。この一年半、私はCEOとして、このシンプルな一点に徹底的に集中して、全社員の意識と行動を変革することに率先して取り組んできました。
例えば、今回掲げた「顧客起点で売上にこだわる」という方針の目的と意味に対する社員の正しい理解と納得を促進するために、構造改革を始めた当初から執行チームと社員との対話を強化してきました。私自身も、各部門で対話を希望する社員を手挙げ式で募ったスモール・ミーティングを2024年度の一年間で65回開催し、のべ約430名の社員ととことんまで直接議論を重ねました。また、社内SNSなどでは私が発信したメッセージに対して、世界中の社員から多くの質問や意見などが寄せられました。私はすべてのコメントに目を通したうえで、原則として即日のうちに私自身や担当役員から直接回答を返しました。
同時に、社内の業務プロセスも「顧客起点」で徹底的に見直しました。具体的には、社内向けの報告事項やそのための準備・会議といった顧客に対する価値創造に直接的につながらない業務を削減すると同時に、現場での意思決定スピードを最速化するために、従来のレポーティングラインや権限規定を経営レベルから見直しました。また生成AIの活用を含む業務のDX化を推し進め、業務の効率化と自動化による働き方の変革にも取り組みました。
これらの取り組みにより、社員の間での「顧客起点」に対する理解度や「主体的に顧客起点で活動する」ことの実践度が着実に向上しつつあり、その意識と行動に変化が生まれ始めている手応えを感じています。一方で「顧客起点」に根差した業務プロセス改善や社内風土改革の取り組みに終わりはありません。社員との直接対話も続けていきます。これからも、顧客からの対価を表す売上の拡大にこだわり、顧客起点に根差した業務プロセス改善や社内風土改革に率先して取り組んでいきます。
※ 詳細はPEOPLEをご覧ください

「NEXT2025」の進捗を含めた24年度の成果と課題を踏まえて、2025年度の全社方針を「All for creating customer value ~需要変化の迅速な察知と機動的アクションによる売上最大化の実現~」としました。この方針には、2025年度も引き続き、“顧客に向き合い、売上を伸ばすこと”に徹底的にこだわり続けるという意志を込めています。
2025年度の全社通期見通しは、米国による関税政策の影響と、それに伴う市場影響が不透明なことから、下振れリスクの幅を持たせた計画として開示しました。具体的には、売上高8,350~8,200億円、営業利益650~560億円、当期純利益を355億円~290億円としています。関税政策が当社事業に与えるコスト影響については、2025年8月に開示した第1四半期決算発表時点の見通しで年間115億円と試算しています。計画では、この全額を売価転換してカバーすることを目指しますが、関税影響による想定を超える需要変動による売上減のリスク(売上影響△150億円、利益影響△50億円)と、2025年度中に全額売価転換ができないリスク(利益影響△40億円)を下振れ幅として織り込んでいます。仮にリスクが顕在化した場合でも、増収増益の達成を目指します。
そして、成長への礎を築いたIABが全社業績を牽引していくことに変わりはありません。2025年度のIABは、中華圏や韓国を中心とする堅調な半導体投資に加え、二次電池業界での中国大手メーカーによる国内・海外拠点への設備投資といった回復基調の需要獲得にとくに注力していきます。同時に、販売代理店との連携強化で顧客基盤をさらに強固にしていくことで事業機会を拡大させていきます。IABは第1四半期も対前年同期比で増収増益を達成し、社内計画を上回る力強いスタートを切っています。
一方でヘルスケア事業(HCB)は、主力の血圧計事業において厳しい事業環境が継続する中国市場の影響を受けていますが、グループ全体でHCBをカバーすることで全社目標の達成を目指していきます。そのためにも、あらためて全社で顧客起点のアクションに徹底的にこだわることで、売上の最大化とその結果としての営業利益目標の達成を実現させるべくチャレンジを続けていきます。
※ 詳細は2025年度計画をご覧ください
構造改革の先に私たちが描いている成長のストーリーが、長期ビジョン「SF2030」で掲げた基本戦略であることに変わりはありません。これからも事業を通じて3つの社会的課題「カーボンニュートラルの実現」「デジタル社会の実現」「健康寿命の延伸」を解決することで持続的な成長を目指していきます。このビジョン実現に向けて、私たちは競争優位な「強いモノ(ハードウェア)」と、そのハードウェアが生み出すデータを活用したソリューション・サービス「モノ+サービス」の両輪を成長のドライバーとして、2030年に向けた企業価値向上の道筋を確かなものにしていきます。オムロンは、HCBの血圧計や社会システム事業(SSB)の蓄電システムなどに代表されるように、アドレスする事業領域において圧倒的な競争優位性を誇るトップシェアの商品群(モノ)をグローバルに敷き詰めてきました。その顧客資産は、例えばIABでは世界約20万社にのぼり、HCBでは年間2千万台を超える血圧計を世界中のユーザーに届けています。これらのモノが毎日膨大なデータを世界の現場で発生させており、これらの自社商品が生み出す現場データをソリューションにつなげていけるのは、オムロンにしかできないビジネスモデルです。
2025年度はオムロンの強みである「センシング&コントロール+Think」技術を軸とした競争力のある「モノ(ハードウェア)」を市場に投入していきます。例えば、IABでは2025年度に前年から50億円増となる過去最高水準となる研究開発費を投資するなどして、2024年度から2026年度までの3年間に、42の新商品を2026年度までに上市します(24年度11機種発売済み、2025年度22機種、2026年度9機種発売予定)。2025年度は、製造ラインや装置の高度化や現場情報の可視化・IOT化を実現するコントローラ群や、検査精度の向上を実現するセンサ群など、顧客のニーズに応える幅広い商品の投入を計画しています。HCBでは、収益の基盤となる血圧計において、「心房細動」の可能性を検知できる独自の次世代アルゴリズムを搭載した新機種を投入し、グローバルでの普及を促進します。心電計では、「携帯型心電計」や「心電計付き上腕式血圧計」のラインナップを強化し、血圧計に続く新たな成長領域の創造を加速します。SSBでは、ユーザーニーズや住環境に柔軟に対応できる機能を備えた新たな蓄電システムを投入するなどして、蓄電システムにおける国内トップシェアの地位をさらに盤石なものにしていきます。
また、将来のモノの強化に向けて、全社共通の技術開発面にも投資していきます。具体的には、太陽光発電に使うパワーコンディショナーや蓄電システム(SSB)、工場の自動化で重要となる電源やサーボドライブ(IAB)など、SF2030で掲げる3つの社会的課題の解決を幅広く支える「パワーエレクトロニクス 」技術を強化するために、2025年10月に京都・桂川に「パワーエレクトロニクスセンタ」を設立します。同センタでは、パワーエレクトロニクス機器の小型化・高効率化に寄与する次世代デバイスの活用や再生可能エネルギー普及のためのエネルギー制御技術の開発について、「研究開発」から社会実装のための「商品開発」までを一気通貫、かつ、事業横断で行う計画です。パワーエレクトロニクス領域に対しては、同センタの設立をはじめ、2025年度からの3年間で約50億円を追加投資するほか、100名規模のエンジニアを採用することで、技術開発力の向上によるモノの強化を図ります。そして、2030年には、関連事業において2,000億円の売上達成を目指します。
「モノ+サービス」事業へのチャレンジも展開していきます。例えば、IABでは、2016年にソリューションビジネスを開始して以来培ってきた事業資産を活用することで、さらなる競争優位性の確立を目指していきます。NVIDIA社との技術提携を通じて、生産現場における高度なデジタルツイン環境の構築を本格的に推進する取り組みや、コグニザント社と戦略的パートナーシップを通じたデータソリューションの創出は、その一例です。HCBでも、スマートフォンアプリのOMRON connect(オムロンコネクト)を通じた日々のバイタルデータの記録を活用した健康ソリューションをグローバルに推進するとともに、2024年4月に完全子会社化したオランダのルーシーヘルステック社との協働で、遠隔診療サービスの強化にも挑戦しています。
「モノ+サービス」事業の転換を加速するカギを握るのが、JMDC社との共創です。JMDC社が2023年10月にオムロングループに加わって以来、同社とオムロンの既存事業との共創は順調に進化してきました。現在、ヘルスケア領域においては、「プロアクティブヘルス事業」と「コーポレートヘルス事業」に取り組んでいます。プロアクティブヘルス事業では、脳・心臓疾患を始めとする各種重症疾患の発症予防の実現に向け、HCBのデバイスから得られる家庭用データとJMDC社が保有する医療データの連携を2024年8月から開始。2025年度に入ってから連携ユーザー数が年度末比160%で増加するなど、わずか一年で大規模なデータが個人IDでつながり、疾患の発症リスクを予測するためのアルゴリズム開発が加速しています。コーポレートヘルス事業では、2023年6月の発足から累計の会員数が約500の企業・団体にまで拡大した「健康経営アライアンス」を基盤として、データを活用した事業機会の創出に取り組んでいます。すでにJMDC社がデータ分析した従業員の生活習慣病リスクをオムロンで活用した事例を会員企業に提供しているほか、ある会員企業ではオムロンの血圧計を幹部社員に配布したうえで、JMDC社によるデータ解析で個人の健康リスクを管理して、適切な健康管理につなげる構想を進められています。今後、健康経営アライアンスの会員向けには、2025年10月にオムロングループに加わるiCARE社が提供する医療職(産業医・保健師)サービスも組み合わせ、オムロングループ独自のデータに基づいた健康管理サービスを提供していくことも計画するなど、同アライアンスを通じた健康経営の社会実装を加速させていきます。
ヘルスケア領域以外でも共創の実績づくりは進んでいます。社会システム領域では、流通・小売業界における労働力不足という社会的課題の解決を目指す保守・エンジニアリングサービスのDX化などを柱とした「スマートM&S」事業の実装においては、複数顧客における実証実験(PoC)がFY24から複数のテーマでスタートし、順調に進捗しています。さらに、JMDC社のデータマネジメント力とソリューション開発力を活用して製造現場のカーボンニュートラル実現を支援する事業も立ち上げ、顧客の現場課題を抽出しソリューションを提案するためのデータ分析・フィードバックを開始。すでに20件40億円相当の商談が進行しており、顧客のエネルギー生産性の向上に向けた実績を順調に積み上げています。
このようにJMDC社との共創実績は加速度的に積みあがってきており、2027年度までにデータソリューション事業で売上高1,000億円超、営業利益率12%超の事業創造を目指すゴールに向けて確かな手応えを掴んでいます。
※ 詳細はSTRATEGY & BUSINESSをご覧ください
※ 詳細はINNOVATION & TECHNOLOGYをご覧ください
このようにJMDC社をオムロングループに迎えたことで、データソリューション事業に必要なデータベース構築力やデータ分析力、そしてソリューション開発力などは、グループ内で着実に強化されてきました。このJMDC社がリードするグループ内のデータソリューション開発をさらに迅速かつ機動的に行うためには、当社のシステムエンジニアリング力を強化するとともに、その機能を全社経営視点で活用していく必要があるとの課題認識から、2025年10月1日付で新会社「オムロンデジタル株式会社(ODC)」を社長直轄の組織として新設します。ODCは、今までSSB傘下でソフトウェア開発を担っていたオムロンソフトウェア(OSK)社を母体として再編した組織です。OSKは、創業から約50年に亘りオムロングループ内のソフトウェア開発を事業として担い、製品組込み開発に関する豊富なケイパビリティを蓄積してきました。今後ODCは、OSKの組織能力を発展させることでデータソリューション開発に必要なシステムエンジニアリングを全社横断で推進・統括する機能を担っていきます。
さらに、オムロングループ全体をデータソリューションと親和性が高い成長領域にアドレスした事業ポートフォリオへと進化させていく一環として、2025年9月19日に発表した通り、2026年4月1日を目途として電子部品事業(DMB)を分社化する検討を開始しました。
DMBは、創業以来リレー、スイッチ、コネクタ等の電子部品を主力製品とし、高品質を強みとしてお客さまからの信頼を獲得し、長年にわたりオムロンの成長を支えてきました。近年では、EV向け高容量リレー需要の拡大など市場の成長が見込まれる一方、事業スピードやコスト競争力を有する新興企業の参入により、競争環境は一段と厳しさを増しています。このような事業環境のもとで、持続的かつ収益性の高い成長を確立するためには、DMBの強みである品質を維持しながら最適な業務プロセスおよび意思決定プロセスを構築し、事業スピードとコスト競争力を一層強化していくことが不可欠です。さらに、新製品の開発・生産やグローバル営業体制の強化に向けては、これまで以上の投資拡大が必要であり、その実現にあたっては、他社との協創や外部資源の活用などの多様なパートナーシップの可能性も視野に入れて検討していくことが求められます。
これらの取り組みを着実に実行し、事業の収益・成長基盤を確立するためには、自律した経営体制の確立が最も有効であると判断し、DMBを分社化する検討を開始することを決定しました。今後、分社に向けた課題の洗い出しや選択肢の検討を地域毎に進め、2026年4月1日を目途に分社を完了することを目指してまいります。今回の分社化は、私たちの事業を次のステージへと進め、グループ全体のさらなる成長へとつなげていくための大切な一歩となります。
現在のオムロンの株価の水準について、株主の皆様にご心配をおかけしていることを重く受けとめております。現在のオムロンに対する資本市場の見方として「構造改革を通して収益性が大きく改善してきた」ことは評価されている一方で、今後の成長に関してまだ十分に得心されていないことが、現在の評価につながっていると考えています。まずは、競合に勝てる強いモノを徹底的に磨き上げ、その強いモノにデータソリューションが生み出すサービスを掛け合わせた新たなビジネスモデルを成長のドライバーとして、2030年に向けた企業価値向上の道筋を確かなものにいたします。
この反転攻勢を成功させるために不可欠なのは、私たち経営から社員までが一貫して創業の原点であるベンチャー精神で顧客に向き合い、顧客起点で売上・利益に徹底的こだわる企業風土の確立です。構造改革をやり遂げた今、もう一度オムロンの存在意義に立ち返ることで、社会的課題の解決で隆々と成長する企業として、皆さまから評価される会社への転換を成し遂げてまいります。これからも、皆さまのご期待に添えるように、全社一丸となって取り組みを進めてまいりますので、引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。
