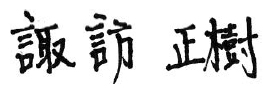オムロンにおけるデジタルデザイン
「先行きが不透明なVUCAの時代の到来」、「VUCAの時代において企業のサステイナブルな成長を支えるDX」など、筆者の身の回りでも「VUCA」というキーワードをよく目にします。とはいいながらも、このVUCAの時代は彗星の如くある日突然到来したという性質のものではありません。例えば、オムロンの創業者である立石一真が提唱したSINIC理論1)においては、情報化社会の到来を目前にした1970年代から、もちろん当時はVUCAという言葉は使われていないですがVUCA時代の到来について語られています。アジャイル開発やデザイン思考などもVUCAに対応するために生まれてきたといっても過言ではありません。
ではなぜ今、身の回りでこの古くて新しいVUCAの時代という言葉を頻繁に目にするようになったのでしょうか?その答えとして、筆者はVUCA、すなわちVolatility(不確実性)、Uncertainty(不確定性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の4つの要素はこれまでも議論されてきたものの、その振れ幅やマグニチュードが事業やビジネスモデルに与える影響として無視できない規模に、それどころか影響の規模が指数関数的に大きくなってきていることが要因であると考えています。この意味において、本特集タイトルに登場する、「デジタルデザイン」はVUCAの振れ幅やマグニチュードがある閾値を超えた時代に備える重要なファンクションの1つであるといえます。
本特集号においては、「デジタルデザイン」は、主にエンジニアリングチェーンにおけるDXを支えるテクノロジーとしての意味合いを持ちます。このデジタルデザインを支えるテクノロジーは、VUCAの時代において3つの役割が期待されます。
(1)不確実性や不確定性に対応する役割
急速な市場環境の変化に、自社のエンジニアリングチェーンが迅速に追従していくためには、もはやフィードバックでは間に合わず、フィードフォワード的な対応が必要となります。キーとなるのは『予測』と『発見』です。入手できうる限りのデータを活用し、環境変化をいかに精度よく予測し、変化対応のボトルネックを発見することがデジタルデザインの果たす役割となります。この際、変化対応のボトルネックを発見する時の、最後の決定は人に委ねられます。デジタルデザインのテクノロジーには、人によるボトルネックの候補を『可視化』し発見の『判断支援』をするという重要な役割があります。また将来見通しの不確定性に対しては、デジタル化による『効率化(=結果的にコスト低減につながる)』がキーとなります。
(2)複雑性に対応する役割
複雑化する市場環境やビジネス環境において、複雑に絡み合う要素を如何に解きほぐし簡易化するかを考える必要があります。デジタルデザインは、複雑な業務プロセスを因数分解し簡素化する、あるいは業務プロセスの最適化や自動化を促進することに貢献します。ここでも簡素化に向けた『発見』と簡素化に向けたボトルネック改善の『判断支援』としてのデジタルデザインの役割があります。
(3)曖昧性に対応する役割
曖昧性の本質は情報の不明確さや不透明さにあります。デジタルデザインには、データそのもの、あるいはデータ分析にもとづく知識の『可視化』によって情報の共有を促進し、意思決定のスピード向上につながる『判断支援』という役割があります。
以上で述べたように、デジタルデザインを支えるテクノロジーとして、VUCAの時代において期待される3つの役割を支えるキーファンクションには、予測・発見・効率化・可視化・判断支援の5つがあります。本特集号においては、このデジタルデザインの5つのキーファンクションの価値を、6つの具体的事例で紹介しています。この6事例を通じてオムロンの考えるデジタルデザインの近未来をご高覧いただけますと幸いです。
デジタルデザインには2つの意味合いがあります。1つ目は「デジタルによるデザイン」です。AIやデータ分析の諸々の技術、可視化技術、シミュレーションなど、5つのキーファンクションを具体的に実装するためのテクノロジーをフル活用してデザインするという意味合いです。2つ目は「デジタルのデザイン」です。事業やビジネスモデルの進化に向けて、「何をデジタル化しないといけないのか?」「DXの本質は何なのか?」について深く考察するという意味合いです。これらいずれの意味合いにおいても、人に任せきりでもなく、機械あるいはテクノロジーに任せきりでもなく、人と機械の協働・融和によるヒューマンセントリックな社会実装を意識することが大切です。
最後になりますが、後々この特集号を読み返したときに、この原稿を書いた時代模様を象徴するようなエピソードを盛り込んだ上で、巻頭言を締めくくります。
エピソード:この巻頭言のいくつかの部分は、「デジタルによるデザイン」という意味合いでのデジタルデザインの最新ツールである、「生成AI」を活用して文章を生成しました(もちろんAIの出力そのままではなく、筆者によって加筆修正はされています)。読者の皆様におかれましては、どの部分が該当するかおわかりになりますでしょうか?
- 1)
- 中間真一.SINIC理論.日本能率協会マネジメントセンター,2022,268p.

オムロン株式会社 執行役員 技術・知財本部長
兼 オムロン サイニックエックス株式会社 代表取締役社長